クリニックの事業承継のポイントや承継完了までの流れを徹底解説

日本の医療業界は、高齢化社会の進展と後継者不足という大きな課題に直面しています。特にクリニックの事業承継は、地域医療の維持と発展に重要な役割を果たしています。2024年には医療機関の倒産・休廃業が過去最多を記録し、その多くが診療所と歯科医院でした。この状況下で、クリニックの円滑な事業承継は喫緊の課題となっています。
本記事では、クリニックにおける事業承継の重要性と背景、事業承継のポイント、評価方法、事業の成功のカギについて解説します。
クリニック事業承継の重要性と背景
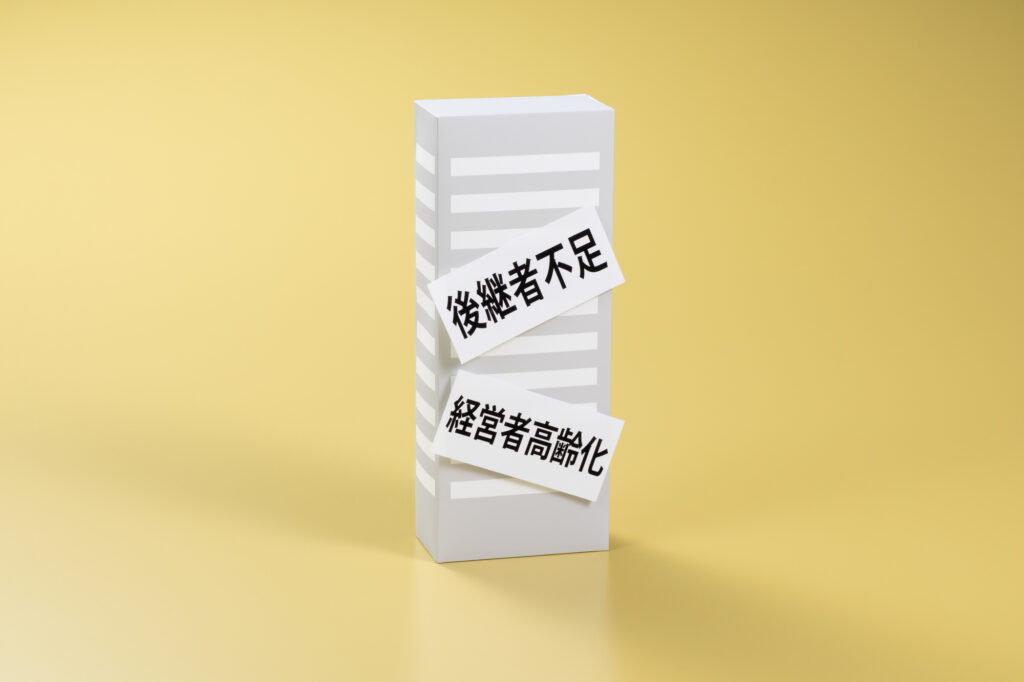
医療業界における事業承継の現状
医療機関の後継者不足が深刻化しており、病院、クリックなどで61.8%が後継者不在または未確定状態にあるということが明らかになっています。また2024年度の医療機関の倒産件数は64件、休廃業・解散は722件となり、それぞれ過去最多を更新しました。倒産、休廃業・解散ともに診療所と歯科医院が急増しております。
特に地方では過疎化が進み、医療機関の閉院・廃院が地域住民の健康を脅かすリスクを抱えています。そのような中で経営者の高齢化も顕著になっており、令和4年度の調査では病院経営者の平均年齢は64.9歳、診療所は62.5歳に達しています。これは全国の社長平均年齢(60.5歳)を上回り、医療業界がほかの業界と比較しても、高齢化の進行が明確です。
クリニック事業承継においては、新たな傾向が見られます。従来主流であった親族内に医院を承継する「親族内承継」に代わり、「第三者承継」の選択が増加しています。
この背景には、ご子息が医師であっても専門分野が異なる場合や、地元に戻ることを望まない、そもそも開業医としてのキャリアを選択しないケースや、診療報酬の削減による経営の困難化、施設老朽化や人材不足といった医療環境の変化から親族に継がせることを躊躇し、代わりに第三者へクリニックを承継する傾向が強まっています。
出典:帝国データバンク|全国「後継者不在率」動向調査(2024年)
厚生労働省|令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況
クリニック事業承継のメリットとデメリット
クリックの承継において、親族間承継と第三者承継についてそれぞれのメリット・デメリットを比較します。
<親族間承継のメリット>
〇スムーズな引継ぎ
親族を後継者として育成する場合、早い段階から経営に関与させることができるため、十分な教育期間を確保しやすい。
〇理念の継続性
親族間での承継は、前経営者の経営方針や理念を引き継ぎやすく、患者やスタッフにとっても安心感がある。
<親族間承継のデメリット>
〇税務面の課題
相続税・贈与税が発生する可能性がある。
〇制約の多さ
親族間の関係性から「引き継がなければならない」という心理的負担がある。
<第三者承継のメリット>
〇後継者不足の解決
親族内に後継者がいなくても事業の継続が可能。
〇地域医療維持
患者・スタッフを引き継ぐことにより、地域医療を存続させることができる。
〇新たな経営手法の導入
第三者が経営を引き継ぐことで、新しい経営手法やノウハウが導入され、事業の成長が期待できる場合がある。
<第三者承継のデメリット>
〇人材・患者流出リスク
新経営者の医療理念との不一致、経営方針変更があった場合、患者離れやスタッフ集団退職のリスクがある。
〇譲渡条件の交渉の難しさ
資産・負債の精査(土地鑑定士等の専門家依頼が必要)、譲渡金額や条件の交渉に時間がかかることがあり、スムーズに承継が進まない場合や、承継時期も不確実である。
〇法的手続きの複雑さ:
第三者承継には、法的な手続きや税務上の問題が伴うことが多く、専門家の支援が必要になる。
《親族間承継と第三者承継の比較》
| 親族間承継 | 第三者承継 | |
|---|---|---|
| 後継者確保 | 親族内に限定 | 親族外でも可能 |
| リスク要因 | 後継者不足・心理的負担 | 人材流出のリスク、交渉時間の長期化 |
| 地域医療の維持 | 理念継続性が高い | 既存患者・スタッフの継続 |
高齢化社会とクリニック承継の必要性
先述のとおり日本では急速に高齢化が進み、医療業界では事業承継の必要性が高まっています。
経営者は定年制限がないため、後継者不在のまま高齢化が進むと「現役続行」が強要される状況が生じます。もし突然の体調不良等で廃業せざるを得なければ、地域住民にとって大きな影響を及ぼします。
特に、医療サービスが不足している地域では、クリニックの存続が地域医療の質を保つために不可欠となります。後継者不足が深刻化する中で、事業承継の方法を多様化させることが求められていますが、特に、M&A(第三者承継)を活用した承継は、地域医療を守るための有効な手段となるでしょう。
地域医療における承継の役割
地域医療は、住民の健康を支える重要な基盤であり、特に地方に位置するクリニックはその中心的な役割を果たしています。しかし、経営者の高齢化や後継者不足が進む中で、クリニックの承継が適切に行われない場合、地域医療の崩壊や「無医地区」化の危険性が高まります。
特に小児医療などの専門分野では、医師の確保が特に困難です。地域に根ざしたクリニックが承継されることで、専門的な医療サービスが継続され、地域の子どもたちが必要な医療を受けることができます。これにより、地域全体の健康状態が向上し、早期発見・早期治療が可能になります。
地域医療における承継は、単なる経営の継続にとどまらず、地域住民の健康を守るための重要な役割を果たします。地域医療の未来を支えるために、承継の重要性を再認識し、積極的に取り組む必要があります。
クリニック事業承継のポイント

親族内承継と第三者承継では流れが異なります。
<親族内承継の場合>
- 診療理念や経営方針の共有
- 税理士や弁護士などの専門家への相談(税務対策)
- 廃止届・開設届など行政手続きの準備
- 後継者の承継計画の策定
- 資産やスタッフ、患者の引き継ぎ
- 承継後の運営調整
クリニックを親族へ承継する際、前院長と後継者が行政手続きを行う必要があります。個人クリニックの場合、事業用資産がすべて課税対象となるため、納税負担が事業承継の障害になる可能性があります。そのため、生前贈与や遺言などの対策を講じ、円滑な承継を進めることが重要です。
<第三者へ承継を行う場合(M&A)>
- 仲介会社・専門家への相談
- 秘密保持契約とアドバイザリー契約の締結
- 譲渡側と譲受側のマッチング
- トップ面談と基本合意
- 譲受側によるデューデリジェンス(適正評価手続き)の実施
- 最終合意と承継完了
第三者承継の場合は、適切な買い手の選定やクリニックの評価が重要なポイントとなります。
承継準備段階のポイント
クリニック承継の準備段階では、現状把握と後継者選定・育成について考える必要があります。まず、財務状況や運営状況を正確に分析し、資産と経営状況を可視化します。
次に、後継者の選定では技術的スキル、経営能力、コミュニケーション能力を評価します。第三者承継の場合は幅広い候補者から適任者を選び、選定後は段階的な引き継ぎを経て後継者を育成し、スタッフや患者との関係構築をサポートする必要があります。
承継計画の策定方法
承継計画の策定では、承継の目的、承継時期、承継方法の検討から始め、資産と経営状況の把握、将来の経営方針決定を行います。同時に、従業員と患者への対応計画、税務対策、必要な行政手続きの準備も含めます。これらの要素を総合的に考慮し、クリニックの特性や地域性を踏まえた詳細な計画を立てることで、円滑な承継が可能となります。すべて一人で考えるとなると大変な労力を要するため、専門家のサポートを受けながら、長期的視点で準備を進めることが重要です。
法的手続きと契約の注意点
クリニック承継における手続きは多岐にわたります。行政への届出、契約書の締結、デューデリジェンスの実施(第三者承継の場合)、資産移転、税務対策、保険医療機関指定の申請など、複雑で専門的な知識を要する作業が多く含まれます。専門家のサポートを受けながら以下に注意する必要があります。
- 行政手続き
- 譲渡側:管轄の保健所に「診療所廃止届」と「レントゲン廃止届」を提出
- 譲受先:保健所に「診療所開設届」と「レントゲン設置届」を提出
- 譲受先:厚生局に「保険医療機関指定申請書」、「引継書」、「保険医登録票のコピー」を提出
- 契約関連(第三者承継の場合)
- 秘密保持契約書の締結:情報漏洩防止のため
- 基本合意書の締結:継承条件の大枠を決定
- 最終譲渡契約書の締結:詳細な条件を明記
- 資産移転
- 土地、建物、医療機器等の資産を特定し、適切に引き継ぎを行う
- 税務対策
- 個人診療所の場合、すべての事業用資産が課税対象となるため、生前贈与や遺言などの対策を検討
従業員と患者への説明と対応
クリニックの承継時には、従業員と患者への適切な説明と対応が重要です。従業員のモチベーション維持と患者との信頼関係はクリニックを安定的に運営するためには欠かせないものです。
従業員に対しては個別面談を行い、雇用条件に配慮しながら新たな雇用手続きを進める必要があります。定期的なミーティングや説明会を通じて疑問や不安を解消する場を設けることが求められます。
患者には院内掲示や直接説明を通じて誠実に承継の旨を伝え、不安を与えないよう医療サービスの継続性を強調することが必要です。カルテの引継ぎには個人情報保護に注意を払いましょう。
クリニックの評価方法
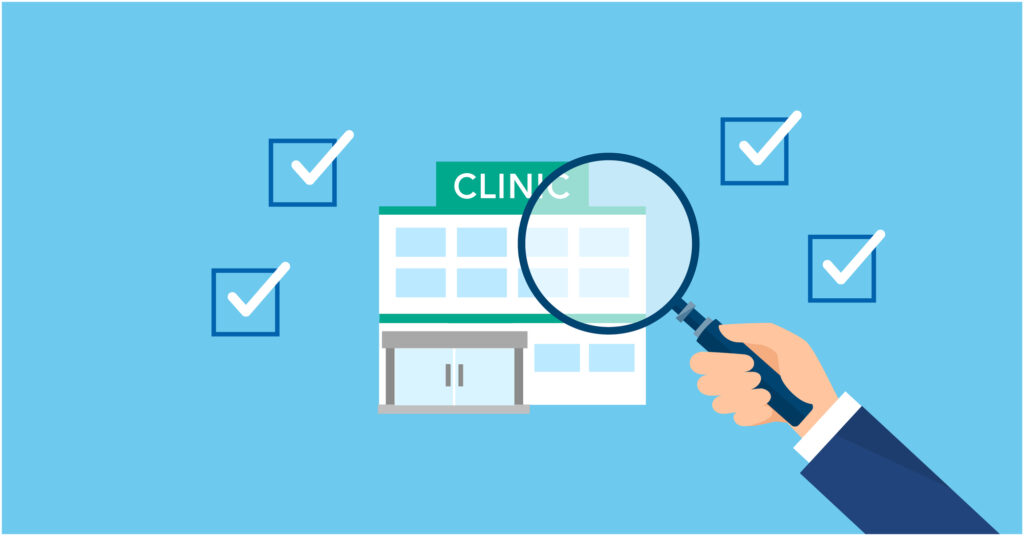
資産価値の算定方法
資産価値は、クリニックが保有する物理的な資産(医療機器、不動産、在庫など)の市場価値を反映します。これにより、クリニックの実際の資産状況を把握することができ、譲渡の際に必要な基準となります。様々な算出方法がありますが、一般的には以下の方法で算出されます。
〇時価純資産+営業権(のれん代)
クリニックの資産と負債を市場価値で評価し、その差額を基に価値を算出します。この方法では、クリニックが保有する不動産、医療機器などの資産を時価で評価し、負債を差し引いて純資産を求めます。
具体的には以下の計算式が用いられます。
譲渡価額=時価総資産額+営業権
※営業権はクリニックが将来生む可能性のある利益を数値化したもので、通常は以下の方法で算出されます
- 前年度の年間所得×1年分
- 将来の年間所得予測値の合計
〇DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)
将来のキャッシュフローを予測し、現在価値に割引くことで評価します。この方法は、クリニックの成長ポテンシャルを考慮に入れるため、予測の精度が評価額に大きく影響します。
〇類似取引比較法
同業種・同規模のクリニックの過去の取引価格をもとに評価する方法です。スタッフや患者の維持状況も評価に影響を与えます。ただし特殊性のあるクリニックでは類似した事例が少ない場合があります。
〇EBITDA倍率法
EBITDA(利息・税金・減価償却前利益)を基に、業界平均の倍率を掛けてクリニックの価値を算出する方法です。※業界や規模によって適用される倍率が異なります
クリニックの価値=EBITDA×業界倍率
(EBITDAの計算式 = 税引前利益 + 支払利息 + 減価償却費)
医療機器や設備の価値評価
医療機器や設備は、現在の市場価格を基に評価されます。特に新しい技術や高性能の機器は、競争力を高める要因となるため、適切な評価が必要となります。また設備の使用年数や状態に応じて、適切な減価償却率を適用し、実際の市場価値を反映させることも重要です。
人材評価と組織の見極め
クリニックを承継する際、資産評価だけでなく人材や組織に対して評価が行われます。これはスタッフのスキルやモチベーションを通じて、運営の安定性や収益力を評価することができるからです。公平な評価制度や人材育成力が高まれば、承継後も安定した運営が期待されます。
また組織文化や診療方針の明確さ、効率的な組織構造、経営ノウハウはクリニックの全体的な価値を高めます。これらは財務的な評価方法を補完し、買い手に対する説得材料としても重要であり、承継後のクリニックの運営の成功を左右する重要なカギにもなります。
地域性と競争環境の影響
地方や過疎地域では後継者不足による閉院リスクがあり、地域医療の維持が課題となりますが、一方、都市部では競争が激化し、差別化戦略が不可欠になっています。また、M&Aや大手グループの統合やデジタル化の進展により小規模クリニックの譲渡環境は変化してきています。
譲渡側は、地域ニーズに合った診療科目の選択、効率的な経営体制の構築、デジタル化への対応など、クリニックの価値を最大化する準備が必要です。また、地域医療への貢献度や患者との信頼関係も、魅力的な譲渡条件を提示する上で重要な要素となります。競合分析を行い、自院の強みを明確にすることで、患者に選ばれる理由を作ることが重要です。
ブランド力と患者からの信頼度の評価
クリニックのブランド力と患者との関係は、「のれん代」として譲渡価格に大きく影響し、将来の収益性を示す指標となります。強固なブランド力と高い信頼度は、譲渡後の患者継続率を高め、経営の安定性を示唆します。また、価格交渉の際にも有利な材料となり、クリニックの価値を最大化することができます。ブランド戦略においては、クリニックの理念や提供するサービスの明確化、患者とのコミュニケーションの強化が含まれます。特に、昨今はSNSやウェブサイトを通じた情報発信が主流になっています。
また患者からの信頼度を評価する方法として、患者満足度調査の実施が有効です。これによりクリニックのサービス品質やスタッフの対応についてのフィードバックを得ることができ、改善点を把握しサービス向上に繋げることが可能です。患者の信頼を得るためには、診療の質だけでなく、待ち時間や院内の清潔さ、スタッフの対応など、さまざまな要素が影響します。
ただし、院長個人への信頼が高い場合は、引き継ぎ期間の設定や名称変更のリスク管理が必要となります。これらの要素を適切に評価し譲渡価格に反映させることが重要です。
クリニック承継における成功のカギ

事例から学ぶ承継のヒント
承継で一番重要なのが早期からの準備とタイミングです。今すぐに承継を考えていない場合でも、承継するタイミングは必ずやってきます。そのため計画的に準備を進めることが成功のカギとなります。
親族内承継の場合、後継者の育成には時間がかかるため、早い段階で後継者の意思確認や育成計画を開始する必要があります。一方で第三者承継では、譲渡先候補の選定に最低でも半年~1年要することが一般的です。そのため譲渡希望時期から逆算して2~3年前に準備を始めることが望ましいとされています。
過去には院長の突然の体調不良により診療時間が制限された結果、売上が減少し、クリニックの価値が下がった状態で譲渡せざるを得なかったケースがありました。特に経営状態が悪化すると譲渡先が見つかりにくくなるため、盛業状態を維持しながら計画的に進めることが重要です。
親族内承継の場合は、家族間で早期に承継の意思を固め、相続や贈与を活用した税務対策や必要な手続きを事前に確認することで円滑な承継が可能になります。また、第三者承継の場合は専門家のサポートを受けながら、譲渡先との信頼関係構築や交渉を進めることが成功につながります。
トラブルを予防するための実践策
〇綿密な情報開示と慎重な交渉
譲渡側は財務状況、簿外債務、診療圏、スタッフの状況、建物や設備の状態など、クリニックの詳細情報を正確に開示する必要があります。これにより、譲受側は将来的な経営計画を立てやすくなり、予期せぬトラブルを回避することができます。
また焦らず時間をかけて譲渡条件を検討することが重要です。譲渡価格、支払方法、債務の引継ぎ範囲、競業避止義務などの重要事項を契約書に明確に記載し、双方の合意を得ることが必要です。
〇スタッフへの配慮と患者とのコミュニケーション
全てのスタッフと個別面談の機会を設け、経営・診療方針・待遇面について話し合うことが重要です。また、新しいシステムや業務内容の変更がある場合は、研修やサポート体制を整えることも必要です。
患者に対しては、診療を存続することをきちんと伝え、不安を解消することが求められます。承継によって診療内容や体制が変わる可能性がある場合は、患者への丁寧な説明と情報提供を行い、信頼関係を維持することが大切です。
〇後継者との関係構築
後継者との良好な関係構築は、スムーズな承継のための鍵となります。診療スタイルや理念を極力引き継ぐよう後継者と協議し、患者への影響を最小限に抑えることが重要です。
専門家のアドバイスを活用する方法
特殊性が高いクリニックの承継において専門家のアドバイスを活用することは非常に重要です。まず、税理事事務所やM&A仲介会社が提供する無料価値診断サービスを利用し、クリニックの状態を多角的に評価してもらうことができます。また、医業承継に関するセミナーに参加することで、基本的な知識を得ることができます。
M&A仲介会社を活用する場合、医療業界に特化した会社を活用することが推奨されます。医療専門のM&A仲介業者は、医療制度や医療法人における税務制度など、クリニック特有のM&A知識に精通しており、より円滑な譲渡を進められます。また、医療業界のネットワークが豊富なため、適切な買い手を見つけやすく、マッチングの可能性が高まります。
まとめ
クリニックの事業承継は、単なる経営の引き継ぎにとどまらず、地域医療の継続性を確保する重要な取り組みです。高齢化社会の進展と後継者不足の深刻化により、特に地方では医療機関の存続が地域住民の健康を左右する重要な課題となっています。
事業承継の成功のためには、早期からの準備と計画が不可欠です。親族内承継か第三者承継かを慎重に検討し、それぞれのメリット・デメリットを踏まえて最適な方法を選択する必要があります。また、クリニックの価値を適切に評価し、資産価値だけでなく、ブランド力や患者からの信頼度も考慮することが重要です。
クリニックの事業承継は複雑で時間のかかるプロセスですが、適切な準備と専門家のサポートを受けることで、地域医療の継続的な提供と経営の安定化を実現することができます。経営者は自身の引退後も見据えた長期的な視点を持ち、早期から承継に向けた取り組みを始めることが重要です。




※2024年3月時点 CBグループ累計
ご相談からM&A(事業承継)クリニックのご紹介、経営者様とのご面談、書類の取り交わしから開業まで、一貫してサポートいたします。











