オーダリングシステムと電子カルテの違いは?システムの特徴やクリニック開業前に知っておきたい基礎知識

医療DXの推進に伴い、病院情報システムとして電子カルテやオーダリングシステムの導入は、今後さらに広がっていくことが予想されます。
そこで本記事では、電子カルテとオーダリングシステムの違いや、それぞれの利点、注意点をわかりやすく解説します。
目次
オーダリングシステムと電子カルテの違い

- オーダリングシステムはどのようなシステムですか?
-
オーダリングシステムとは、医師が処方や検査、処置などの指示を電子的に入力し、関係する各部署へ迅速かつ正確に伝達するためのシステムです。医師がコンピューター上で入力した指示内容は、看護師や薬剤師をはじめとする関係部署全体でリアルタイムに共有される仕組みとなっており、情報伝達のスピード向上とミスの防止に大きく貢献します。
- 電子カルテはどのようなシステムですか?
-
電子カルテは、これまで紙で管理されていた患者さんの診療記録や各種情報をデジタルデータとして保存・管理するシステムです。電子カルテを活用することで、患者さん情報を一元的に管理し、関係者間でスムーズに共有できます。さらに、医療機関内や連携先の端末から必要な情報を瞬時に閲覧できるため、情報共有の迅速化と業務の効率化につながります。
- オーダリングシステムと電子カルテの違いを教えてください。
-
「オーダリングシステム」と「電子カルテ」はどちらも医療現場で使われるITシステムですが、役割や目的が異なります。それぞれの違いを表で比較します。
項目 オーダリングシステム 電子カルテ 主な役割 検査・処方などの「指示を出す」 診療内容の「記録・管理」 使用者 主に医師、看護師 医師、看護師、事務スタッフなど 情報の内容 指示内容(何を、いつ、どれだけ) 問診・診察・経過・所見・検査結果など 連携性 電子カルテと連携して動くことが多い オーダリング機能が含まれている - オーダリングシステムと電子カルテの普及率を教えてください。
-
厚生労働省が公表している『電子カルテシステムなどの普及状況の推移』によると、2020年時点のオーダリングシステムの普及率は、一般病院で62%でした。特に400床以上の大規模病院では93%以上、200~399床の中規模病院でも82%と高い数値が見られますが、200床未満の病院では約53%にとどまっています。
一方、同年の電子カルテ普及率は、一般病院で約57%、一般診療所で約49%と、オーダリングシステムよりもやや低い水準です。病院規模別に見ると、400床以上で91.2%、200〜399床で74.8%、200床未満では48.8%となっており、病床数が少ない医療機関ほど導入が進んでいない傾向が見られます。
オーダリングシステム・電子カルテのメリットとデメリット
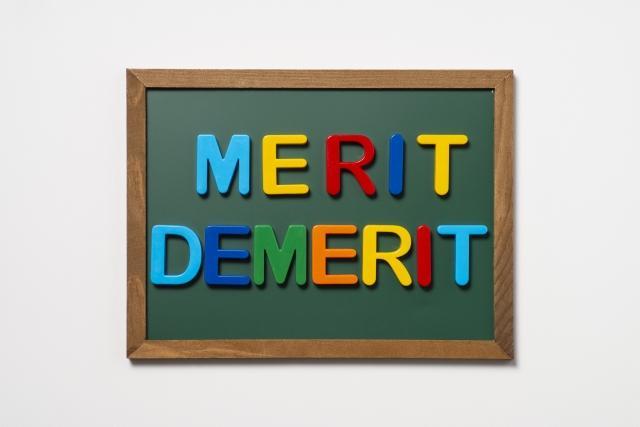
- オーダリングシステムを導入するメリットとデメリットを教えてください。
-
オーダリングシステムを導入するメリットは、医師の指示出しや伝達の手間が減って業務負担を軽減できることです。手書きで行っていた処方や検査の指示を電子化することで、入力の効率が向上し、記載ミスも防げます。指示が各部署に即時伝達されるため、患者さんの待ち時間短縮にもつながります。
ただし、導入時には初期費用や運用コストがかかり、ITに不慣れなスタッフがいる場合は操作研修や人材育成も必要です。また、停電やシステム障害などのトラブルに備えて、バックアップ体制の整備も欠かせません。
- 電子カルテを導入するメリットとデメリットを教えてください。
-
電子カルテのメリットは、情報をデジタル化することで必要な情報をすぐに確認・共有でき、迅速な医療提供が可能になることです。紹介状や診断書も定型文を活用して作成できるため、業務の効率化や医療DXの推進にも役立ちます。
さらに、手書きにより記載ミスを防げるほか、紙カルテのような保管スペースも必要ありません。クラウド型やハイブリッド型の電子カルテであれば、他機関との情報共有もスムーズに行えます。
一方、IT操作に慣れていない場合は業務負担が一時的に増えることもあり、研修や支援体制が必要です。また、紙カルテからのデータ移行や導入にかかるコストも考慮する必要があり、事前の準備が重要です。
オーダリングシステムと電子カルテの連携

- オーダリングシステムと電子カルテは連携できますか?
-
オーダリングシステムと電子カルテは連携可能です。オーダリングシステム導入後に電子カルテを連携させる方法や、最初から両機能が一体となったシステムを採用するという方法があります。
分別型(別システム型)の場合は、事前に互換性やインターフェースを確認し、正しく連携できれば電子カルテ上で患者さん情報を見ながら指示入力を行えます。
一体型は、操作や管理が一本化されて利便性が高い一方で、システム障害が起こった際には業務全体が影響を受けるリスクがある点に注意が必要です。
- 一体型と分別型とはなんですか?選び方のポイントを教えてください。
-
オーダリングシステムと電子カルテを別々に導入し、連携して使うことを分別型と呼びます。
医療情報システムは、まずオーダリングシステムを導入し、その後に電子カルテを追加するのが一般的です。分別型では、互換性のある電子カルテを選ぶことが重要で、導入時から将来的な連携を見据えたシステム選定が必要です。
近年増えている一体型とは、システム連携の手間が不要で操作がシンプルな、電子カルテにオーダリング機能を標準搭載したタイプです。ただし、障害発生時には影響が広範囲になる恐れや、コスト面で負担が大きくなる可能性がある点に注意が必要です。
導入に際しては、医療機関の規模や指示件数、業務量を考慮し、コストと運用性のバランスを比較検討することが大切です。
- 電子カルテを導入済みでもオーダリングシステムを連携できますか?
-
すでに電子カルテを導入済みでも、オーダリングシステムを後から連携することは可能です。対応可能なオーダリングシステムを追加し、連携設定を行うことで、電子カルテ上で患者さん情報を確認しながら指示の入力を行えるようになります。
ただし、電子カルテとオーダリングシステムの互換性やインターフェース対応状況を事前にしっかり確認することが重要です。メーカーやバージョンによってはスムーズに連携できない場合もあるため、選定時には注意が必要です。
オーダリングシステムの導入コスト

- オーダリングシステムを導入する場合の初期費用の目安を教えてください。
-
病院の規模や使用するオーダリングシステムの種類によって費用は大きく異なります。
病院規模 初期費用の目安 小規模(~50床程度) 500~1500万円程度 中規模(100~300床) 2000~5000万円程度 大規模(500床以上) 5000万~1億円以上になる場合もあり
※クラウド型の場合は初期費用が安く、月額課金モデルになることもあります。導入時には大きな初期コストが発生するという点をあらかじめ認識しておくことが大切です。
- オーダリングシステムを運用するためのランニングコストはどの程度ですか?
-
オーダリングシステムの運用には、年間の保守管理費として500万円程度の費用がかかります。
加えて、スタッフへの操作指導や医療クラークの確保など、人的対応も必要となり、一定の人件費がかかる点にも留意が必要です。維持には金銭的・人的コストがかかることも踏まえて検討しましょう。
編集部まとめ
本記事では、電子カルテとオーダリングシステムの違いや特徴を解説しました。
電子カルテは『患者さんに関する医療情報を電子化し、一元管理するシステム』のことで、オーダリングシステムは『医師の指示を迅速・正確に伝える仕組み』のことです。
導入には高額なコストや人材確保といった課題がありますが、活用できれば業務効率化や医療サービスの質の向上につながります。
医療DXの推進により、今後は中小規模の病院や診療所でも普及が進むことが期待されます。
それぞれのシステムのメリット・デメリットを把握したうえで、自院の方針や体制に合ったシステム導入を検討しましょう。











