【キャッシュレス決済端末】クリニックで導入するメリットや比較ポイント、注意点とは

近年、社会全体でキャッシュレス化が進んでいますが、医療機関では依然として現金会計が主流であることが多く、キャッシュレス化が課題となっています。
本記事では、クリニックにおけるキャッシュレス決済端末導入のメリットや注意点などについて詳しく解説します。
目次
クリニックにおける会計業務の現状と課題

クリニックの窓口業務において、会計処理は重要な業務の一つです。まずは、クリニックにおける会計業務の現状と課題について解説します。
クリニックでのキャッシュレス決済の普及率
経済産業省の発表によると、日本全体のキャッシュレス決済比率(すべての支出のうちキャッシュレスで支払われた割合)は2024年に42.8%に達しました。
出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250331005/20250331005.html)
一方、医療機関におけるキャッシュレス決済の普及率は依然として低く、日本医師会が2019年に実施した調査では、導入済みの医療機関はわずか13%にとどまっています。
参照:日本医師会『医療機関におけるキャッシュレス決済についてのアンケート結果概要について』
クリニックにおける現金会計の課題
現金会計には、さまざまな課題が残されています。
例えば現金の紛失や盗難のリスク、毎日の売上金の計算や入金処理、釣り銭の準備など、現金管理には多くの手間と時間がかかります。
また、小銭のやりとりや釣り銭の計算などにより、会計業務に時間がかかるうえ、ミスが発生しやすい課題もあります。
クリニックで使えるキャッシュレス決済端末の基本機能

キャッシュレス決済端末は、現金以外の決済方法を可能にする機器です。クリニックでの導入を検討する際は、その基本機能や特徴を理解することが重要です。
キャッシュレス決済の種類
クリニックで利用可能なキャッシュレス決済には、主に次の4種類があります。
- クレジットカード決済:一般的なキャッシュレス決済の一つで、利用者が多い傾向にあります。
- デビットカード決済:その場で預金口座から即時引き落とされる決済方法です。
- QRコード決済:スマートフォンを使用してQRコードを読み取って支払います。
- ICカード決済(電子マネー):事前にお金をチャージして使うプリペイド型と、クレジットカードと紐づけて後日引き落とされるポストペイ型があります。
経済産業省の発表によると、2024年のキャッシュレス決済のうち、クレジットカード決済が82.9%、QRコード決済が9.6%という結果でした。
出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250331005/20250331005.html)
基本機能と特徴
多くのキャッシュレス決済端末はコンパクトで設置場所を取らず、簡単な操作で決済できるよう設計されています。売上管理機能が備わった機種であれば日々の取引を自動で記録でき、売上管理の効率化も期待できます。
POSレジやセルフレジとの違い
キャッシュレス決済端末は、POSレジやセルフレジと異なる役割を持っています。
POSレジは売上の管理や在庫管理、商品登録など幅広い機能を備え、医療機関向けには電子カルテやレセプトコンピュータとの連携に特化したものも開発されており、診療報酬の自動計算や会計データの自動連携などクリニックの受付業務全般をサポートします。。
セルフレジは患者さん自身が会計操作を行うシステムで、電子カルテとの連携により複雑な医療費計算にも対応した製品も登場しています。
キャッシュレス決済端末は主に決済処理に特化しており、単独での売上管理機能は限定的です。多くの場合はPOSレジなど周辺システムと連携して使用されるため、受付業務全体の効率化を視野に入れて自院に会う組み合わせを検討しましょう。
クリニックがキャッシュレス決済端末を導入するメリット
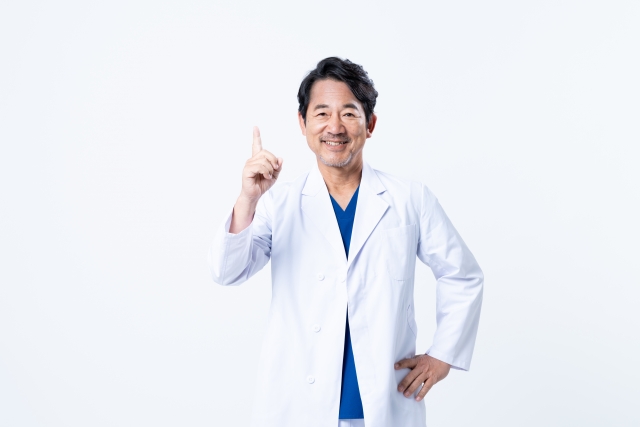
ここでは、医療機関がキャッシュレス決済端末を導入することで得られる具体的なメリットについて解説します。
会計業務の効率化
キャッシュレス決済端末導入の大きなメリットは、会計業務の効率化です。現金による会計と比べてキャッシュレス決済は1人あたりの会計時間を短縮でき、患者さんの待ち時間の短縮につながります。
また、業務終了後の現金集計作業も簡略化されます。
スタッフの負担軽減
現金管理に伴う銀行への入金業務や釣銭の補充作業が不要となり、スタッフの負担軽減につながります。売上データの手動集計も自動化され、スタッフは患者対応や診療サポートにより集中できるようになります。
患者さんの満足度向上
キャッシュレス決済端末を導入することで、日頃からキャッシュレスを利用している患者さんは、よりスムーズに会計ができるようになります。特に高額な診療費を支払う場面では、大きな金額の現金を持ち歩く必要がなくなるため、安心感も得られるでしょう。
こうした利便性の高さは、患者さんのストレスを減らし、クリニックに対する満足度の向上につながります。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大以降、非接触での支払いは感染症対策としての安心感も得られます。
現金管理のリスク低減
盗難や紛失、計算ミスによる過不足といったリスクを低減でき、決済データの自動的記録により不正行為の防止や会計の透明性向上が期待できます。
未収金発生のリスク低減
医療機関における未収金は深刻な問題です。現金の持ち合わせがない患者さんに対しても、キャッシュレス決済端末があればその場で決済を完了できるため、未収金発生のリスクが減ります。
キャッシュレス決済端末の導入費用とランニングコスト

キャッシュレス決済端末の導入にあたっては、初期費用だけでなく、月額使用料や決済手数料など継続的なコストも考慮する必要があります。端末の種類やサービス内容によって費用は大きく異なるため、導入前に全体のコストを把握し、自院に適したプランを選ぶことが重要です。
初期費用と月額使用料の目安
キャッシュレス決済端末の初期費用は、導入する端末の種類やブランドによって異なります。シンプルなカードリーダータイプの場合、端末代は5,000~20,000円、クレジットカードや電子マネー、QRコード決済に対応しており、レシートを発行するためのプリンターが組み込まれたオールインワン・プリンター内蔵型の端末の場合は、30,000~50,000円が一般的な費用目安です。
レンタル・リース型の場合、端末代金の初期費用を抑えられますが、3,000~5,000円程度の月額使用料がかかります。
決済手数料の目安
決済手数料は、キャッシュレス決済端末を利用する際の主要なランニングコストです。手数料はおおむね2~3%で、事業規模や契約プランによって優遇措置が適用される場合もあります。手数料率は利用するサービスや決済方法によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
クリニック向けキャッシュレス決済端末を比較するポイント
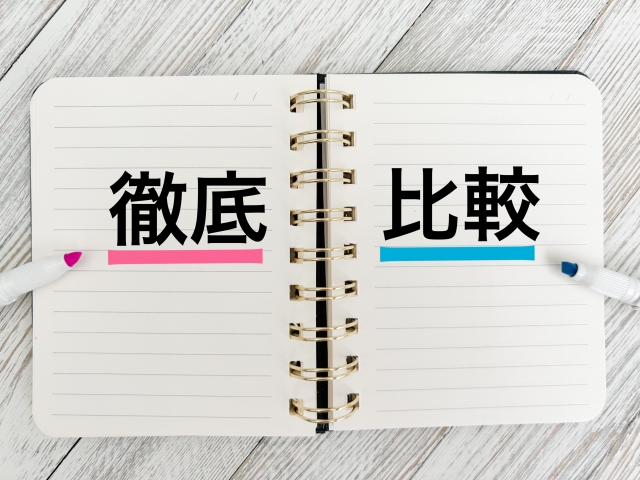
キャッシュレス決済端末を選択する際には、複数のポイントを比較検討することが重要です。クリニックの特性や患者さんの層を考慮して、適切なサービスを選択しましょう。
決済手数料と導入コスト
長期的なランニングコストに大きく影響する決済手数料や端末代金、月額使用料などを総合的に評価することが重要です。初期費用が安くても、月額使用料や決済手数料が高い場合、長期的には高コストになる可能性があります。
対応する決済ブランドや種類
クレジットカード決済ではどのブランドに対応しているか、QRコード決済や電子マネー決済はどのような種類が使用可能かを事前に確認するのがポイントです。
若い世代の患者さんが多いのか、高齢の患者さんが多いのかという患者さんの層によっては、あまり使用されない決済方法もあるでしょう。患者さんの層に応じて、よく利用される決済手段に対応しているかを見極めることが重要です。
自院の会計フローやほかのシステムとの相性
決済端末は、既存の会計システムや電子カルテ、レセコンなどのシステムとの連携が可能な端末を選べば、業務効率化につながります。
例えば、POSレジとの連携で会計と売上管理が一本化でき、スタッフの業務負担を軽減できます。受付業務が煩雑にならないよう、導入前に自院の運用スタイルとの相性を確認しておくのがおすすめです。
サポート体制
キャッシュレス決済端末は、患者さんの会計に直接関わるシステムのため、トラブル時の迅速な対応が求められます。自院の診療時間に応じたサポート体制があるかどうか、電話やメールでの問い合わせに迅速に対応してもらえるかどうかを確認しましょう。導入時の操作研修やマニュアル提供の有無も重要です。
キャッシュレス決済端末導入時の注意点

キャッシュレス決済端末導入時には、事前に以下の注意点を検討することで、導入後のトラブルを避けることができます。
患者さんへの告知と案内を行う
導入にあたっては、患者さんへの周知が重要です。院内掲示やホームページで決済方法を事前に案内し、受付でもスタッフが説明できる体制を整えましょう。特に高齢の患者さんにはわかりやすく案内し、現金での支払いを希望する患者さんには現金支払いに応じるなど柔軟な対応が求められます。
システムエラー時の対応体制を整えておく
キャッシュレス決済端末は電子機器のため、システムエラーや通信障害が発生する可能性があります。エラー発生時の対応マニュアルを作成し、スタッフが基本的な操作や対処法を把握しておくことが重要です。
また、完全なシステム停止に備えて、現金対応や領収書の手書き発行も可能な体制を残しておくことが望ましいです。サポート窓口の連絡先や対応時間を把握し、万一の際に迅速な対応が取れるようにしておく必要があります。
通信環境と停電時の対策を確認しておく
キャッシュレス決済には安定したインターネット接続が不可欠です。院内の通信環境が安定しているかを事前に確認し、不安がある場合は通信環境の見直しが必要です。
Wi-Fiだけでなくモバイル回線(LTE)に対応している端末であれば、通信トラブル時のバックアップにもなります。
また、停電対策としてバッテリー内蔵型の端末を検討する、長時間の停電に備えてUPS(無停電電源装置)の導入を検討するのも有効です。災害時の対応マニュアルを整備し、スタッフ全員が内容を把握しておくようにしましょう。
まとめ

キャッシュレス決済端末の導入は、クリニックの会計業務の効率化と患者満足度の向上に大きく貢献しますが、初期費用や運用コスト、どのような決済方法を選択するかなど慎重に検討すべき点も多くあります。また、通信環境の整備やシステムトラブル、通信障害への備えも欠かせません。
自院に適したキャッシュレス決済端末を導入し、よりよい医療サービスの提供につなげていきましょう。











