クリニック向けレセコンはどう選ぶ?普及率や特徴、比較ポイントと費用の目安を解説

クリニックにとってレセコン(レセプトコンピューター)は、日々の業務効率化のために欠かせないツールです。導入を検討する際は、初期費用や運用コスト、注意点などを確認する必要があります。
本記事ではレセコンの導入にあたって知っておくべきポイントについて解説します。
目次
クリニックにおけるレセコンの普及率と課題

レセコンは、医療現場における業務効率化に欠かせないツールです。しかし、導入にあたっては注意点もあります。本章では、クリニックのレセコンの普及状況と導入する際の注意点について解説します。
クリニックのレセコン普及率
医療機関が健康保険組合などの保険者に対して診療報酬を請求する際に使用する書類がレセプト(診療報酬明細書)で、患者さん1人につき1ヶ月間の診療内容を記載したレセプトをまとめて審査支払機関に提出します。審査を受けたレセプトは健康保険組合などの保険者に送付され医療機関に医療費が支払われる仕組みです。
かつては紙のレセプトを手作業で作成していましたが、作業負担が大きいため、業務効率化や医療費の適正化などを目的として1983年から電子レセプトによる請求制度が始まりました。その後徐々に普及が進み、現在では広く導入されています。
厚生労働省の令和5年3月診療分『電子レセプト請求状況』によると、診療所(クリニック)の電子レセプト請求率は97.0%です。つまり、現在ほとんどのクリニックで電子レセプトが利用されており、電子レセプト作成のためにレセコンが活用されています。2024年9月以降は光ディスクや紙レセプトでの請求は原則認められず、電子レセプトでの請求が義務化されたため、今後はオンライン請求が標準となっていく見込みです。
出典:
『請求状況(医療機関数・薬局数ベース) 【令和5年3月診療分】』(厚生労働省)(https://www.ssk.or.jp/tokeijoho/tokeijoho_rezept/tokeijoho_rezept_r04.files/seikyu_0503.pdf)(2025年7月18日に利用)
レセコンを導入しても業務効率が向上しないケースとは
レセコン導入により業務効率化が期待できるなか、レセコンを導入しても業務効率が向上しないケースがあります。
- スタッフが操作に不慣れで入力ミスや業務の混乱が増えている
- 既存の業務フローとレセコンの機能がうまくいかず、二重入力や紙との併用が発生し、手間が減らない
- レセコンの保守体制が不十分でトラブル時の対応に時間がかかっている
業務効率を向上させるためには、システムの選定時に自院の業務内容との相性を見極め、導入前後の研修やサポート体制を整えることが重要です。
クリニック向けレセコンの種類と特徴
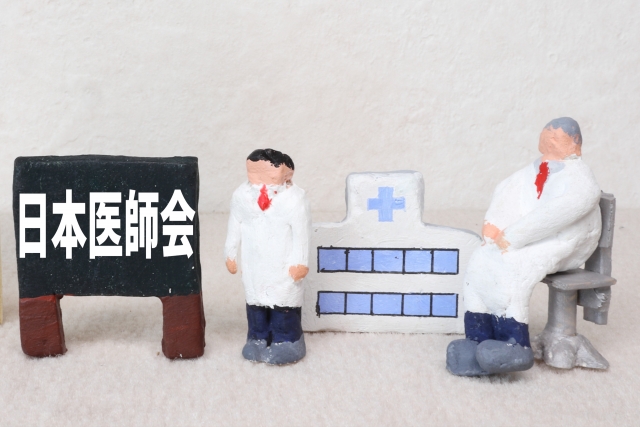
レセコンには大きく分けて、日本医師会が提供するORCAと、民間企業が提供するものの2種類があります。本章では、それぞれの特徴について解説します。
ORCAの特徴
ORCAの正式名称はOnline Receipt Computer Advantageで、日本医師会が医療現場のIT化・標準化を目的に開発しました。主な特徴は以下のとおりです。
- 初期費用を抑えられる
ORCAのベースはオープンソースとして無償公開されたシステムで、ライセンス料がかかりません。現在は一部機能がパッケージ化され有償になっていますが、初期費用を抑えられるので、初期費用を抑えたい場合は魅力的な選択肢であるといえます。
- 汎用性が高くカスタマイズが可能
API(Application Programming Interface)を介して外部ソフトウェアやシステムからORCAにアクセスできるため、拡張性が高く、多くの電子カルテとの連携も可能です。
- 医療制度の改定に迅速に対応
ORCAは新薬や診療報酬の改定にも迅速に対応しています。
これらのメリットがある一方、導入や運用には専門的な知識が必要なこともあり、設定や保守にはある程度のITリテラシーが求められるため、導入時には信頼できるサポート体制を整えることが重要です。
ORCA以外のレセコンの特徴
ORCA以外にも、多くのベンダーが自社開発し、提供しています。これらの多くは有償で提供されており、操作性の高さやサポートの手厚さ、クラウド対応などが大きな特徴です。
例えば、クラウド型レセコンは院外からのアクセスや自動アップデートが可能で、IT管理の負担を軽減できます。
また、ORCAが連携できる電子カルテは限られていますが、ORCA以外のシステムでは電子カルテや会計ソフトとのスムーズな連携を重視した製品や電子カルテと一体型の製品もあり、診療から会計までを一貫して効率化できます。
ほかにも、レセプト返戻を避けるためのチェック機能や、オンライン予約、オンライン診療と連携できる機能、視覚的な見やすさを重視し直感的な操作が可能な製品など、製品によってさまざまな機能や特徴を有しています。
レセコンと電子カルテを連携させるメリット

レセコンと電子カルテはそれぞれ単体でも使用可能ですが、これらを連携させることで業務の効率化やコストの削減が見込めます。
業務の効率化
レセコンと電子カルテを連携させることで、患者さんの来院から診察、会計までの流れを一元管理できます。それぞれの段階において、システムに患者さんの情報を登録する作業が不要となり、医師や看護師、受付スタッフの業務量を削減する効果が期待できます。
ミスの削減
レセプトは電子カルテの内容をもとに作成されるため、内容が一致する必要があります。レセコンと電子カルテが別々の場合は手作業による転記が必要となり、スタッフの読み間違いや転記ミスが発生する可能性があります。電子カルテとの連携により転記作業が不要となるため、ミスの削減が期待できます。
コスト削減
レセコンや電子カルテの導入・連携には費用がかかりますが、手作業による業務を減らすことで、人件費の削減につながります。
また、紙カルテやレセプト用紙の印刷コスト、保管スペースにかかる費用も削減することができます。
クリニックでORCA以外のレセコンを選ぶ際の比較ポイント

クリニックごとに適切なレセコンは異なります。ここではORCA以外のレセコンを選ぶ際にチェックするべきポイントを解説します。
電子カルテとの連携の可否
上述のように、レセコン導入で業務効率化やミス削減などの効果を十分に発揮するためには、電子カルテとの連携可否が重要なポイントです。
レセコンと電子カルテの相性が悪い可能性があるので、すでに電子カルテを導入済みだったり導入する電子カルテが決まっている場合は、レセコンが連携可能かどうかをベンダーに確認しましょう。まだ電子カルテが決まっていない場合は、電子カルテとレセコンが一体となっている製品も視野に入れ、相性を重視して選ぶのがおすすめです。
操作性
レセコンは毎日事務スタッフが使用するため、システムの操作性が悪いとかえって業務効率が悪くなることもあります。直感的で視覚的にわかりやすいシステムや、操作に迷った際に参照できるヘルプ機能を有するものを選ぶと、スタッフの業務負担を軽減できます。
制度改正への対応状況
医療機関が作成するレセプトは、処置、治療、薬剤などに対して厚生労働省の診療報酬制度に基づいて算定されます。診療報酬は、2年に1度の大幅な改定に加え薬価の変更や算定ルールの改正など日々改定されているため、これらの変更に迅速に対応できるかはシステム選びの重要な要素です。オプション費用となることもあるため、導入前にしっかりと確認しましょう。
サポート、保守体制の充実度
システムの導入時に忘れてはならないことが、サポートの手厚さです。サーバーエラーによりオンライン請求ができない、操作方法がわからないなどの日々のトラブルや、大きな障害時のサポート体制(平日、土日祝、24時間体制など)を確認することが重要です。
クリニックでレセコンを導入する際にかかる費用の目安
レセコンを導入する際にかかる費用は、システムによって異なります。ここでは、費用の目安を紹介します。
導入費用の目安
レセコンの導入費用は、ORCAか有償レセコンか、さらにオンプレミス型かクラウド型かによって異なります。
| 種類 | 形態 | 導入費用の目安 | 特徴 |
| ORCA | オンプレミス型 | 100〜500万円程度 |
|
| クラウド型 | 5〜10万円程度 |
|
|
| ORCA以外 | オンプレミス型 | 200〜500万円程度 |
|
| クラウド型 | 10〜30万円程度 |
|
オンプレミス型はサーバーや専用端末の購入が必要なため初期費用が高くなりがちで、クラウド型は初期費用を抑えやすい傾向があります。
月額費用の目安
月額費用には、主に保守運用やバージョンアップにかかる費用が含まれます。
| 種類 | 形態 | 導入費用の目安 | 特徴 |
| ORCA | オンプレミス型 |
|
|
| クラウド型 |
|
|
|
| ORCA以外 | オンプレミス型 |
|
|
| クラウド型 |
|
クラウド型は月額利用料に保守・アップデート費用が含まれるケースが多く、コストがやや高めです。
そのほかにかかる費用の目安
基本的には上記の費用が中心ですが、オプションとしてシステムの容量を追加したり、使用する端末を増やしたりする際に費用がかかることがあります。
クリニックにレセコンを導入する流れ
レセコンの導入までの一般的な流れは以下のとおりです。
1.レセコンの選定
まずは、ORCAを導入するか、それ以外のレセコンを使用するかを決めます。ベンダーごとにさまざまな特徴があるので、クリニックに合うレセコンを選ぶために複数のレセコンを比較検討するとよいでしょう。
2.導入時期までのスケジューリング
導入するシステムを決めた後は、実際に導入時期を検討します。既存の電子カルテと連携や院内サーバー構築の有無など、状況により導入までの期間が異なります。
3.機器設置・設定やスタッフへの教育
導入時期が確定したら、必要に応じて院内サーバー、パソコン、モニターなどの設置・設定を行います。また、ベンダーの担当者からレセコンの操作方法や注意点について説明を受けます。すべてのスタッフに基本的な操作方法を共有しておくと、緊急時などに対応しやすくなります。
4.稼働開始
必要な準備が整ったら、実際に稼働を開始します。稼働後にも操作における不明点が出てくる可能性があるため、アフターサポートについても確認しておきましょう。
特にレセコンを日々使うスタッフへの十分な教育が、業務効率化の肝となります。導入時期は焦らず準備期間を十分に確保し、準備を行うことが重要です。
レセコン導入時の注意点
レセコンを導入してもスタッフが活用できないと意味がありません。導入時には以下の点に注意しましょう。
医療事務スタッフへの研修を実施する
医療事務には、幅広い知識と制度変更への対応力が求められます。毎日使うシステムだからこそ、安心して運用できるよう研修を行うことが大切です。
院内マニュアルを作成する
レセコン導入後は、院内での操作方法やトラブル時の対応を共有できるマニュアルを作成しておくことが大切です。スタッフ間で操作のばらつきがあると、入力ミスや業務の停滞につながるため、基本操作からレセプト作成、月次業務まで手順を明確にまとめておきましょう。
よくあるエラーへの対処法やベンダーの問い合わせ先なども記載しておくと、トラブル時にも迅速に対応できます。
まとめ
クリニック向けのレセコンは、クリニックの業務効率化において必須ともいえる重要なシステムです。ORCAや有償レセコン、オンプレミス型やクラウド型など種類はさまざまですが、自院の規模や業務フロー、電子カルテとの連携状況を踏まえた選定が重要です。
導入にあたっては、単に機能だけでなく、サポート体制やトラブル発生時の対応方法なども含めて総合的に検討することが重要です。
レセコンを長期的に安定して使える体制を整えることが、業務効率化と患者さんへの質の高いサービスにつながるでしょう。











