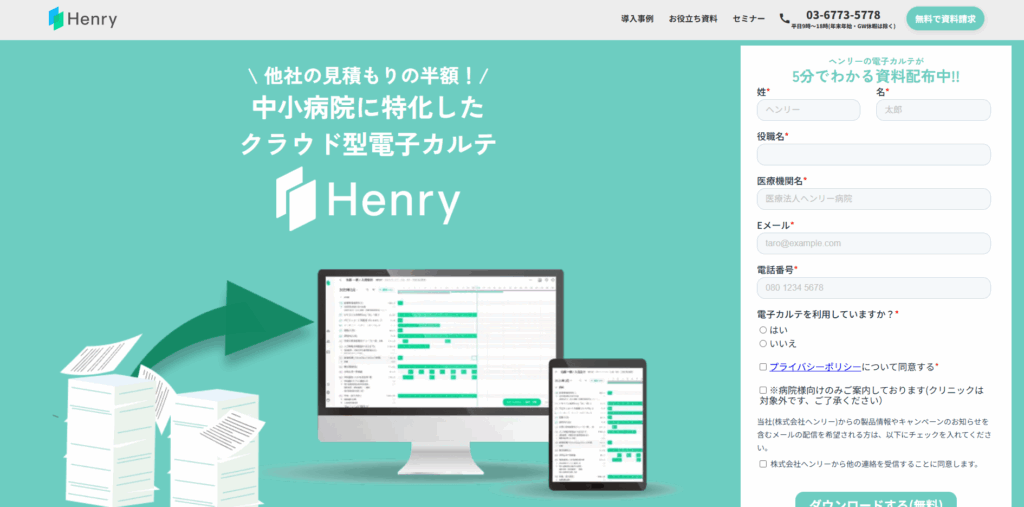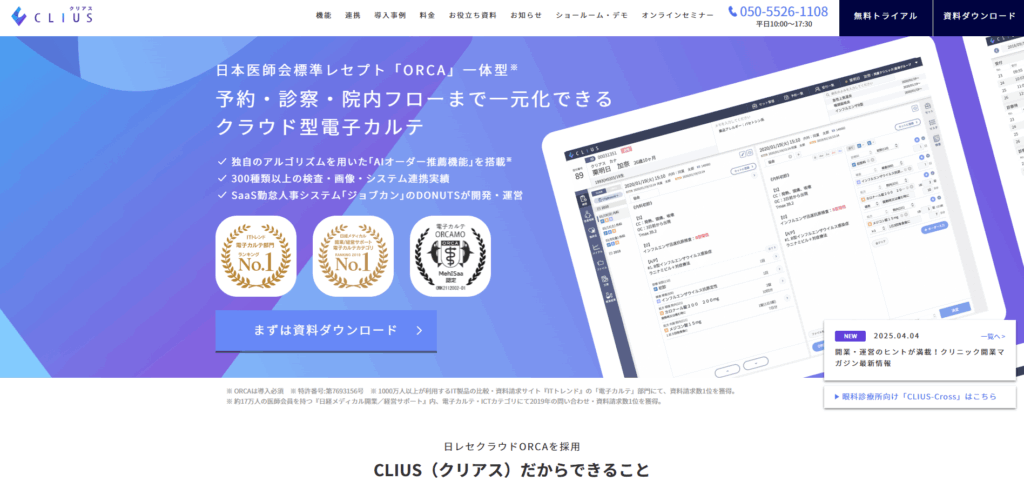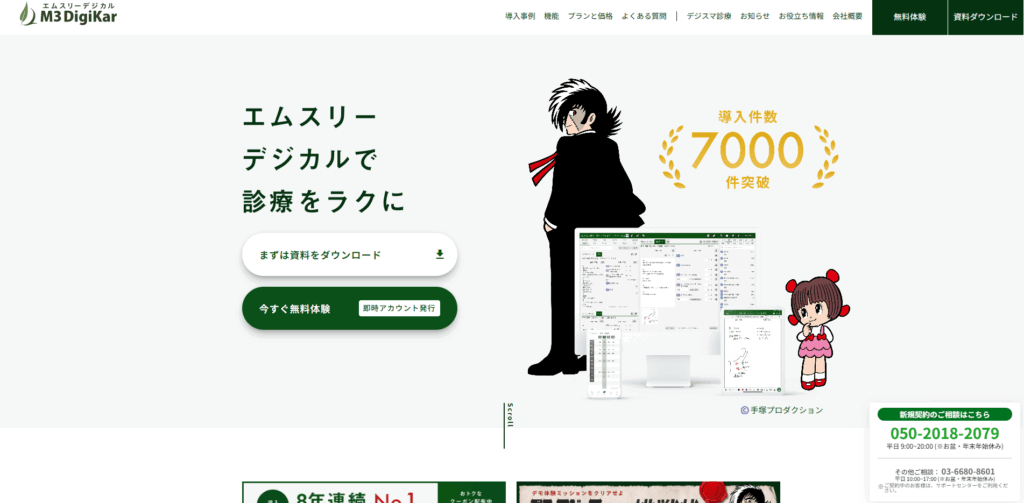訪問診療を効率化!在宅診療向け電子カルテ導入のメリット|在宅診療向け電子カルテ10選を紹介

在宅診療では、移動しながら複数の患者さん宅を訪問し、正確な記録と情報共有が求められます。モバイル対応の電子カルテを導入すれば、訪問先での入力や確認作業を効率化でき、チーム全体の連携強化にもつながります。本記事では、在宅診療に適した電子カルテの選び方や導入メリット、おすすめ製品10選を紹介します。
目次
在宅診療における電子カルテの必要性

在宅診療は、外来診療とは異なり、医師や看護師が患者さんの自宅や施設を訪問して医療を提供します。そのため、現場で患者情報を確認し、診療記録を正確に残すことが求められます。こうした環境では、リアルタイムでデータ入力や共有が可能な電子カルテが欠かせません。本章では、在宅医療の現場で電子カルテが必要とされる理由を3つの視点から解説します。
紙カルテや汎用システムでは限界がある理由
在宅診療では、訪問先で過去の診療記録や検査データをすぐに確認する必要があります。しかし、紙カルテは持ち運びや情報検索に時間がかかるうえ、記入漏れや紛失のリスクも伴います。また、外来向けに設計された一般的な医療システムでは、訪問スケジュール管理や地図情報との連携が不十分なことが多く、在宅医療特有の業務には対応しきれないケースがあります。在宅診療に特化した電子カルテを導入すれば、モバイル端末からその場で入力や閲覧が可能となり、限られた時間のなかでも正確かつ効率的な記録・共有を実現できます。
訪問先での情報共有の難しさ
在宅診療では、医師をはじめ、看護師やリハビリスタッフ、訪問薬剤師など複数の職種が連携して患者さんを支えます。しかし、紙カルテや手書きメモでは情報伝達のタイミングがずれたり、内容が抜け落ちたりが少なくありません。クラウド型電子カルテを導入すれば、インターネットを通じて新しい情報をリアルタイムで共有でき、誰がいつどの患者さんを訪問したのかをチーム全体で把握できます。これにより、重複訪問や対応漏れなどのミスを防ぎ、チーム医療の連携力と診療の質を高めることが可能になります。
診療の効率化と法令遵守の観点
在宅診療では、診療記録や処方内容、指示書、訪問スケジュールなど、多岐にわたる情報を正確に管理する必要があります。電子カルテを活用すれば、これらのデータを一元化でき、記録の保存や追跡、監査対応までをスムーズに行えます。さらに、クラウド上での自動バックアップやアクセス権限の管理機能により、セキュリティ面でも法令に準拠した確かな運用が可能です。こうした仕組みは、限られた人員で多くの患者さんを支える在宅医療の現場で、効率性と信頼性の両立を実現する重要な基盤となります。
在宅診療向け電子カルテの主な機能

在宅診療に特化した電子カルテは、限られた時間で複数の訪問先を回る医師や看護師の業務を効率化するよう設計されています。外来向けのシステムとは異なり、現場での操作性や情報共有のしやすさを重視している点が特徴です。本章では、在宅診療の現場で特に効果を発揮する3つの主要機能を紹介します。
タブレットなどで利用できるモバイル対応
在宅診療では、患者さん宅や介護施設など、あらゆる環境でスムーズに記録を取る必要があります。モバイル対応の電子カルテなら、タブレットやスマートフォンから直接カルテを閲覧、入力でき、訪問先での手書きメモや後からの転記作業を省けます。オフラインでもデータを一時保存できるシステムも多く、通信状況に左右されずに運用できる点も魅力です。さらに、音声入力やテンプレート登録などの機能を活用すれば、入力時間を短縮でき、医師やスタッフの業務負担を大きく減らせます。
訪問スケジュール管理・地図連携機能
在宅診療では、1日の限られた時間で複数の訪問先を効率よく回る必要があります。スケジュール管理や地図連携の機能を備えた電子カルテを導入すれば、訪問予定をスタッフ全員で共有し、患者さん宅の位置を地図上で確認しながら適切な移動ルートを組み立てられます。また、訪問履歴や診療内容をスケジュールと結びつけて記録できるため、過去の経過を時系列で把握しやすくなります。これらの機能は、医師や看護師の時間管理を支え、診療の遅延や訪問漏れを防ぐうえで大きな効果を発揮します。
チーム医療を支えるリアルタイム情報共有
在宅医療では、医師や看護師、リハビリ職、薬剤師など、多くの専門職が連携して1人の患者さんを支えます。クラウド型電子カルテを導入すれば、情報をリアルタイムで共有でき、誰がどの患者さんを訪問し、どのような処置を実施したかを即座に確認できます。さらに、指示書や処方内容をチーム全体で共有できるため、重複作業や伝達漏れの防止にも効果的です。診療情報や検査結果、画像データなどの一元管理により、在宅医療チームの連携が円滑になり、効率的で質の高い医療提供を実現できます。
在宅診療向け電子カルテ導入前に確認すべきポイント

在宅診療向け電子カルテを導入する際は、単に機能の多さや価格だけで選ぶのではなく、現場での運用に適しているかどうかを慎重に見極めることが重要です。選定を誤ると、かえって業務負担が増えたり、情報漏えいなどのリスクを抱えるおそれがあります。本章では、在宅診療の現場でスムーズに運用できる電子カルテを選ぶために、導入前に押さえておくべき3つのポイントを紹介します。
外部システムとの連携
在宅診療では、電子カルテだけで業務が完結するケースは多くありません。レセプト請求システムや訪問スケジュール管理ソフト、検査システムなどとの連携が不可欠です。連携が不十分な場合、二重入力やデータの不整合が生じ、業務効率が低下するおそれがあります。特に、介護記録ソフトや訪問看護システムを併用している場合は、相互に情報共有できるかの事前確認が重要です。ORCAなどの医事システムと連携できる電子カルテを選べば、請求処理の自動化や入力ミスの削減を実現し、日々の業務をよりスムーズに進められます。
セキュリティ・個人情報保護対策
患者さんの情報を扱う在宅診療では、情報保護の体制強化が欠かせません。クラウド型電子カルテを導入する際は、通信の暗号化や二段階認証、アクセス権限の細分化などの仕組みが整っているかを確認する必要があります。さらに、サーバーが国内のデータセンターに設置されているか、定期的なバックアップや災害時の復旧対策が行われているかも重要な検討要素です。モバイル端末を利用する場合は、紛失や盗難に備えた遠隔ロックや自動ログアウトなどの機能が求められます。こうした体制が整っていれば、患者さんの大切な情報を適切に管理し、継続的に信頼性の高い運用が可能になります。
操作性とスタッフ研修のしやすさ
どれほど機能が豊富でも、現場で使いにくければ効果を発揮できません。操作性に優れた電子カルテは、画面構成がわかりやすく、直感的に入力や閲覧ができる設計になっています。職種やITスキルを問わず扱いやすいかどうかを、導入前のデモ操作やトライアルで確認するとよいでしょう。さらに、メーカーが提供するオンライン研修やマニュアルが充実していれば、スタッフ教育の負担を抑えながらスムーズに運用を始められます。扱いやすさと教育体制の整った製品を選べば、現場への定着が早まり、診療業務の効率化にも直結します。
在宅診療向け電子カルテ
本章では、在宅医療の現場で導入実績があり、訪問診療の効率化やチーム医療の連携強化を支援する電子カルテメーカー10社を紹介します。タブレット対応やクラウド連携、スケジュール管理など、各製品の特徴を比較しながら、自院の診療体制や運用環境に合うシステムを選ぶ際の参考にしてください。
homis|メディカルインフォマティクス株式会社
homisは、在宅医療に特化したクラウド型電子カルテです。提供元はORCAの導入支援実績を持つ企業で、システム導入時のコストを抑えやすい点が特長です。診療情報をもとにAIが書類を自動作成する機能や、薬や病名のチェック機能を搭載しており、記録業務の時間短縮とヒューマンエラーの防止を実現します。医師や看護師、その他の職種がリアルタイムに情報を共有できるため、チーム医療の連携がよりスムーズになります。従量課金制の料金体系を採用している点も特徴です。在宅患者や施設入居者が多い中規模から大規模のクリニック、または新規開院時に費用を抑えたい医療機関に適した製品です。
モバカルネット|NTTデバイステクノ株式会社
モバカルネットは、在宅医療業務の効率化を目的に設計されたクラウド型電子カルテです。NTTグループの電子証明書を活用し、通信やデータ管理の信頼性を高めています。主な機能は、地図連携による効率のよい訪問ルート検索、オフライン入力への対応、ORCAや介護請求ソフト連携による請求業務の自動化です。さらに、チャット機能で院内外の職種間が保護された経路で情報を共有できます。カルテ数や端末台数に上限がなく、柔軟に運用できます。外来と訪問診療を並行するクリニックや、訪問ルートの効率向上、請求処理の負担軽減を目指す医療機関に適しています。
セコムOWEL|セコム医療システム株式会社
セコムOWELは、無床診療所や在宅クリニックに特化したクラウド型電子カルテです。セキュリティサービスで知られるセコムグループが提供しており、強固なセキュリティ体制と災害対策を備えています。主な機能として、紙カルテに近いシンプルな画面構成、訪問スケジュール管理、介護費用を含む月まとめ請求機能など、在宅医療の現場に必要な機能を搭載しています。Windows、Mac、iPadなど端末を選ばず、インターネット環境があればどこからでもアクセス可能です。操作が直感的でわかりやすいため、パソコン操作に不慣れなスタッフが多いクリニックや、セキュリティを重視しつつ導入コストを抑えたいクリニックに適しています。
Medicom-HRf Hybrid Cloud|ウィーメックス株式会社
Medicom-HRf Hybrid Cloudは、医事会計システムと一体化したハイブリッド型の電子カルテです。レセコン、電子カルテ分野で豊富な導入実績を持つベンダーが提供し、全国の代理店による地域密着型のサポート体制が整っています。院内サーバーとクラウドの両方にデータを保存するハイブリッド構成により、通信障害時や災害時でも医療の継続が可能です。主な機能として、PCやタブレットからの院外カルテ閲覧および入力、画像取り込み、経営分析ダッシュボード、約170社の外部機器との連携機能を備えています。在宅診療を兼ねるクリニックや、レセコン一体型による請求業務の効率化、強固なバックアップ体制を重視する医療機関に適しています。
Henry|株式会社ヘンリー
Henryは、中小病院やクリニック向けに設計された医事一体型のクラウド型電子カルテです。ベンダーは医療DX領域のスタートアップで、同製品は直感的な操作性と低コストを実現している点が特徴です。主な機能は、音声入力や手書き入力への対応、病床稼働率などの経営指標を可視化するダッシュボード機能です。これにより、キーボード操作が苦手なスタッフの業務効率化や、経営分析に役立ちます。データはクラウド上で2拠点に分散保存され、3省2ガイドラインに準拠した高いセキュリティを確保しています。導入、運用コストを抑えたい中小規模の病院や、多角的な経営分析を重視する医療機関に適しています。
電子カルテiBow|株式会社eWeLL
電子カルテiBowは、訪問看護ステーションに特化したクラウド型システムです。訪問看護分野に特化したIT支援事業を展開するベンダーが提供しており、全国47都道府県で導入実績があります。特徴として、AIを活用した計画書や報告書の自動作成、効率的な訪問ルートの自動作成機能を備えています。これにより、看護師は書類作成や移動にかかる時間を削減し、本来の看護ケア業務に集中できる環境を整えます。また、カスタマイズ性の高いUIは、初心者から熟練スタッフまで使いやすい設計となっています。レセプト機能も強化されており、請求業務を迅速に行いたい訪問看護ステーションや、業務負担の軽減と生産性向上を目指す事業所に適しています。
CLIUS|株式会社DONUTS
CLIUSは、無床診療所向けのクラウド型電子カルテです。ITシステム開発を専門とする企業が提供しており、直感的でシンプルな操作性と低コストが特徴です。主な機能として、AIによる自動学習機能を用いた入力支援、Web予約、問診、オンライン診療、在宅医療機能を追加料金なしで提供しています。Windows、Mac、iPadなど端末を選ばず利用でき、日医標準レセプトソフトORCAとの連携にも対応しています。操作のわかりやすさを重視するクリニックや、多様な診療スタイルを低コストで始めたい医療機関に適しています。
エムスリーデジカル|エムスリーデジカル株式会社
エムスリーデジカルは、医療情報サイトを運営するエムスリーグループが提供するクラウド型電子カルテです。初期費用無料、月額制の料金体系により、コスト削減に貢献します。主な機能として、AI自動学習機能による処置行為の自動セット化を備え、カルテ記入時間を削減します。在宅診療では、iPhoneやiPadなどのモバイル端末に対応しており、訪問先からでも患者情報や処置履歴をリアルタイムで確認できます。これにより、緊急時対応や、時間と場所を選ばない柔軟な診療体制の構築に貢献します。AIによる効率化やモバイル端末の活用、初期費用を抑えた導入を希望するクリニックに適しています。
CLINICSカルテ|株式会社メドレー
CLINICSカルテは、クリニック向けのレセコン一体型クラウド電子カルテです。医療情報プラットフォームを運営するメドレーグループの製品であり、患者さんとつながるをコンセプトに開発されています。主な機能として、日医標準レセプトソフトORCAと連携した受付から会計までの一元管理、初期費用0円の低コスト設定、経営分析機能を備えています。メドレーが提供するオンライン診療やWeb予約のサービスとシームレスに連携し、患者さんの利便性向上に貢献します。クラウド型であるため、自宅や往診先など院外からでもカルテの確認および編集が可能で、在宅医療の業務効率化につながります。
Zaitak Karte|株式会社アイソル
Zaitak Karteは、在宅医療と外来診療の両方に対応したクラウド型電子カルテです。在宅医療に特化した特徴として、インターネット接続環境があれば、いつでも、どこでも、さまざまなデバイス(PCやタブレットなど)からカルテの操作が可能です。また、在宅医療関連の文書作成機能が充実しており、患者情報などを医事文書に簡単に反映できます。さらに、インターネットFAX連携により、病院に戻らずに処方箋や紹介状を送信できるため、医師やスタッフの移動負担を軽減します。オプションのTeam Karteを導入すれば、訪問看護ステーションなどの多職種間での情報共有をよりスムーズに行うことができます。
在宅診療向け電子カルテ導入のメリット

在宅診療に特化した電子カルテの導入により、医師や看護師の負担を軽減し、患者対応の質を高めることができます。訪問診療は限られた時間のなかで多くの業務をこなす必要があるため、デジタル化による業務効率化とチーム連携の強化が大きな効果を発揮します。本章では、在宅診療向け電子カルテ導入によって得られる主なメリットを3つの観点から紹介します。
診療効率化と時間短縮
電子カルテを導入する一番のメリットは、記録や検索、共有のスピードが格段に向上する点です。訪問先でタブレットを使って診療内容を入力すれば、その場で記録が完了し、帰院後の転記作業が不要になります。また、スケジュール管理機能により、移動ルートや訪問順を適正化できるため、1日あたりの訪問件数を増やすことも可能です。これにより、医師や看護師の業務時間を削減しながら、より多くの患者さんに対応できる体制を整えられます。
情報の一元管理による医療ミス防止
紙カルテや手書きメモでは、情報の抜け漏れや共有の遅れが起こりやすく、誤記や伝達ミスが医療事故につながるリスクもあります。クラウド型電子カルテを導入すれば、患者情報や処方履歴、検査結果などを一元管理でき、更新された情報を全スタッフがリアルタイムで確認できます。これにより、重複投薬や診療内容の誤認を防止し、信頼性と正確性を大きく向上させます。過去データの検索も容易で、再診時の診療効率にもつながります。
患者満足度と診療体制の強化
電子カルテの導入は、スタッフの働きやすさだけでなく、患者満足度の向上にもつながります。会計処理や書類作成のスピードが上がり、待ち時間を短縮できるほか、チーム間での情報共有が進むことで、よりきめ細やかなケアが可能になります。さらに、医師不在時にもほかのスタッフがカルテ情報を確認して対応できるため、医療体制の安定化にも寄与します。電子カルテは、単なる記録ツールではなく、在宅医療全体の品質を高めるインフラとして重要な役割を果たします。
まとめ
在宅診療向け電子カルテの導入により、診療効率化と情報共有強化を実現し、医療ミス防止と患者満足度向上につながります。本記事で紹介した10社を参考に、モバイル対応やクラウド連携、操作性を比較検討しましょう。限られた時間と人員で質の高い医療を提供するため、自院のニーズに合ったシステムを選定してください。