【税理士監修】クリニックにおけるインボイス制度の基本|チェックポイントや注意点を紹介
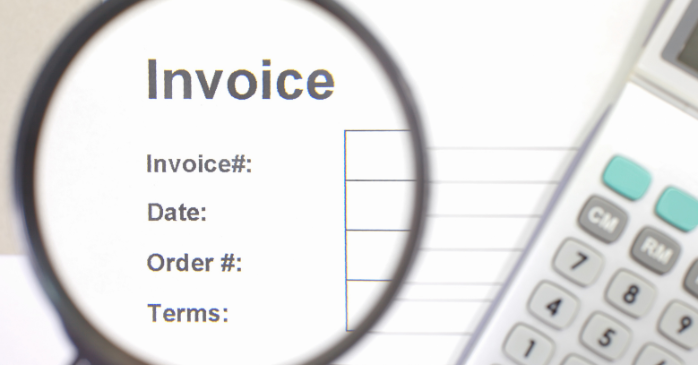
目次
監修税理士

永藤 貴弘
おだね税理士事務所 公認会計士・税理士
東京税理士会神田支部所属。神戸大学経営学部卒業。中小から大手の税理士法人にて約15年の勤務したのち、2024年10月におだね税理士事務所を開業。創業からリタイアの時まで、中小企業の経営者を力強く支え、共に成長し、地域社会への貢献を目指し奮闘中。税務に関する記事の監修も多数行っております。
「クリニックもインボイス制度の対応が必要なの?」と戸惑っている先生方も多いのではないでしょうか。2023年10月から始まったインボイス制度は、これまで消費税の課税事業者ではなかった多くの医療機関にも影響を与える制度です。特に、自費診療や企業との取引があるクリニックは、制度への理解と対応が欠かせません。
この記事では、制度の基本から具体的なチェックポイント、注意点まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説していきます。
【クリニックのインボイス制度】概要と影響

インボイス制度は一部のクリニックにも影響を及ぼす制度です。まずは基本から丁寧に確認していきましょう。
- インボイス制度とは何ですか?
-
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を行うために必要な「適格請求書(インボイス)」を発行・保存する制度です。2023年10月に導入され、事業者間の取引で消費税の控除を受けるには、インボイスの交付と保存が必須になりました。
インボイスには、登録番号や税率ごとの消費税額などが明記されている必要があり、発行には「適格請求書発行事業者」への登録が必要です。制度開始により、事業者の経理実務にも大きな影響が出ています。
- クリニックにおけるインボイス制度の影響は?
-
一般的に保険診療収入は消費税の非課税取引となるため、インボイス制度の影響を受けにくいと思われがちですが、自費診療や企業との取引があるクリニックには大きな影響があります。たとえば、美容診療やワクチン接種、健康診断などを提供している場合、それらは課税売上に該当し売上に消費税がかかります。
取引先が仕入税額控除を行うにはクリニックが発行するインボイスの保存が必要となります。インボイスの発行に対応できない場合、取引先は仕入税額控除ができなくなり、契約を見直されるリスクもあるため注意が必要です。
- インボイス制度に対応しない場合のリスクは?
-
インボイス制度に対応しない=「適格請求書発行事業者」として登録しない場合、クリニック側は取引先に対してインボイスを発行できません。結果として、消費税の課税事業者である取引先は仕入税額控除ができなくなり、「取引を継続できない」と判断される可能性があります。
特に企業向けの健康診断や委託業務を請け負っている場合、契約打ち切りや価格交渉の圧力がかかることもあるかもしれません。インボイス制度への対応は、自院の信用や収益にも直結する重要な経営課題といえます。
インボイス制度への対応が必要なクリニックの特徴

ここでは、どのようなクリニックがインボイス制度に対応する必要があるのか、その特徴を具体的に見ていきましょう。
- 自費診療の売上が多いクリニックは対応が必要ですか?
-
自費診療を主に行っているクリニックはインボイス制度への対応が必要となるケースがほとんどです。原則的に保険診療は消費税の非課税取引ですが、自費診療は課税対象となるため、適格請求書発行事業者として登録し、インボイスを発行できる体制を整える必要があります。
特に美容医療や自由診療、矯正歯科などを提供している場合において、患者が法人であれば、仕入税額控除の観点からインボイスの発行を求められる場面が増えるでしょう。
- 企業向けの健康診断や予防接種を行う場合の対応は?
-
企業との取引があるクリニックは、インボイス制度への対応を強く求められるでしょう。法人がクリニックに健康診断やインフルエンザ予防接種などを依頼する場合、その費用に対して消費税が課税されます。取引先である企業が仕入税額控除を行うには、クリニックが発行する適格請求書(インボイス)の保存が必要です。
そのため、インボイスを発行できないクリニックとは契約を見直される可能性もあるため、事前の登録と体制整備が重要になるでしょう。
- 産業医としての活動がある場合の対応は?
-
産業医として企業と契約し、報酬を受け取っている場合もインボイス制度の対象となる可能性があります。産業医の報酬が課税取引に該当する場合、企業側は仕入税額控除を行うためにインボイスの発行を求めてくることが想定されます。
特に定期的な業務委託契約を結んでいる場合は、制度対応が契約の継続に直結することもあるでしょう。自身の業務内容と取引形態を整理し、必要に応じて適格請求書発行事業者の登録を検討することが重要です。
インボイス制度対応のためのチェックポイント

ここでは、クリニックがインボイス制度に適切に対応するために押さえておくべきポイントを見ていきましょう。
- 適格請求書発行事業者の登録方法は?
-
適格請求書発行事業者になるには、税務署に申請して登録をする必要があります。申請は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するか、e-Taxを利用してオンラインで行うことが可能です。登録には一定の審査期間があり、早めの対応が求められます。登録後には、登録番号が発行され、請求書や領収書などにその番号を明記する必要があります。
- 領収書や請求書の記載事項の変更点は?
-
インボイス制度では、従来の請求書や領収書(区分記載請求書)に比べて、記載すべき項目が増えています。具体的には、①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号、②取引年月日、③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)、④税率ごとに区分した税抜取引金額または税込価額の合計額及び適用税率、⑤税率ごとの消費税額、そして⑥書類の交付を受ける相手方の氏名または名称などが必要です。
記載漏れがあると、取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、なお、従来の請求書や領収書(区分記載請求書)から追加されるものは、①登録番号、④税率ごとに区分した税抜取引金額、⑤税率ごとの消費税額となっております。実務上の影響も大きくなります。日々の業務の中でスムーズに対応できるよう、フォーマットの見直しも検討しておきましょう。
- 事務作業の増加にどう対応すべきですか?
-
インボイス制度への対応により、請求書の発行・管理や登録番号の記載確認など、事務作業が確実に増加します。特に小規模なクリニックでは、スタッフの負担が大きくなることが懸念されます。そのため、医療事務の担当者に制度の基本的な理解を促すとともに、会計ソフトや電子請求書発行システムなどの導入を検討するとよいでしょう。ミスを防ぎ、業務を効率化する体制を整えることで、日常業務に支障をきたすことなく制度に対応できます。
クリニックがインボイス制度に対応する際の注意点
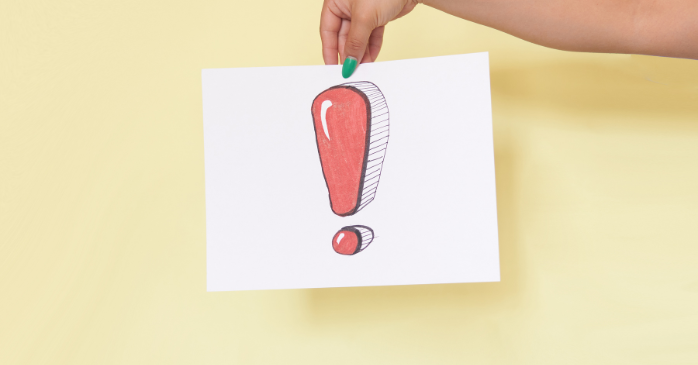
ここでは、クリニックがインボイス制度に対応する際に気をつけておきたい実務面や制度面での注意点を整理してお伝えします。
- 課税事業者になることのメリットとデメリットは?
-
課税事業者としてインボイス制度に対応することで、取引先との信頼関係を維持できる、契約の継続がスムーズになるといったメリットがあります。また、消費税の仕入税額控除を自院でも受けられる点も利点です。一方で、消費税の納税義務が発生し、経理処理や帳簿管理の手間が増えるというデメリットもあります。
特に非課税収入が多く消費税の免税事業者であったクリニックが適格請求書発行事業者となる場合では、消費税の納税負担が実質的に増えるケースもあるため、自院の事業構造に応じた慎重な判断が必要です。
- 簡易課税制度や2割特例の適用条件は?
-
インボイス制度開始後、課税事業者となる中小規模のクリニックには「簡易課税制度」や「2割特例(負担軽減措置)」の適用が検討できます。簡易課税制度は、業種ごとに定められたみなし仕入率を使って税額を計算できる制度で、事務負担の軽減につながります。ただし、選択には適用する課税期間の初日の前日までに届出が必要で、業種により控除率が異なる点に注意が必要です。一方、2割特例(負担軽減措置)は新たにインボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者が令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間(一般的な個人事業主であれは令和8年12月31日まで)に限り納税額を売上税額の2割とする制度です。2割特例の適用に当たっては、事前の届出は必要ありません。消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。どちらも要件や期限を確認し、早めに準備しておくと安心です。
- 取引先への周知やコミュニケーションのポイントは?
-
インボイス制度への対応にあたっては、取引先への丁寧な周知と円滑なコミュニケーションが欠かせません。特に、これまで免税事業者であったクリニックが課税事業者となる場合、請求書の形式や消費税の取り扱いに変化が生じるため、事前に説明を行うことが信頼関係の維持につながるでしょう。また、登録番号の提示や適格請求書の発行準備が整っていることを伝えることで、安心感を与えられます。制度を一方的に伝えるのではなく、相手の理解を確認しながら進める姿勢が大切です。
編集部まとめ
インボイス制度は保険診療中心のクリニックには直接関係しないように見えますが、自費診療や法人取引がある場合は無視できない制度です。制度を正しく理解し、早めに準備を進めることが、信頼されるクリニック経営につながります。適切な対応によって、患者や取引先との関係も良好に保てるでしょう。
【免責事項】
当記事は、一般的な税務に関する情報提供を目的として作成されており、個別の税務相談やアドバイスを行うものではありません。
税法や関連法規は頻繁に改正される可能性があり、最新の情報ではない場合があります。
記事の内容に基づいて意思決定や行動を起こされる際は、必ず税務署や税理士等の専門家にご相談ください。
当記事の情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いかねます。











