レセコンとは?電子カルテとの違いや導入のメリット、選び方のポイントを解説

クリニック経営では、診療報酬の請求業務を効率よく進めるために「レセプトコンピューター(レセコン)」の活用が欠かせません。事務作業の負担軽減や正確な請求処理を行ううえでも、レセコンの仕組みや機能について理解しておくことが大切です。
本記事ではレセコンの概要と電子カルテとの違い、導入メリット、選び方のポイントを解説します。
レセコンの基礎知識と電子カルテとの違い

レセコンとはレセプトコンピュータの略称で、診療報酬明細書(レセプト)を作成し、医療費を保険者へ請求するための専用コンピューターシステムです。
クリニックや病院の受付・会計部門で医療事務スタッフが使用し、氏名や保険証情報といった患者さんの情報や医師が行った診療内容を入力すると、健康保険の点数計算を自動で行い、レセプトを作成します。
紙や手作業でレセプトを作成するには膨大な時間と労力がかかりますが、レセコンにより迅速かつ正確な請求処理が可能となり、事務作業の効率化とミス削減に大きく貢献します。
レセコンと電子カルテはどちらも医療ITシステムですが、目的と役割が明確に異なります。レセコンは前述のとおり保険請求業務の管理が目的で、診療内容に応じた診療報酬点数を計算し、レセプトを作成・提出するためのものです。
一方、電子カルテは患者さんの診療記録を電子的に管理・保存することが目的で、医師の診療内容や検査結果、看護記録など医療情報を扱います。利用者にも違いがあり、電子カルテは医師・看護師など医療従事者が主に操作するのに対し、レセコンは医療事務担当者が操作するのが一般的です。
最近では電子カルテとレセコンが一体となった統合型システムや、別々のシステムでも連携できるシステムが登場しており、転記ミスの防止や事務負担の軽減につながっています。
レセコンはソフトウェアの種類や提供形態によりいくつかの分類ができます。代表的なものとして次の2つの種類が挙げられます。
ソフトの種類
ORCA(オルカ)系とメーカー独自製品に大別されます。ORCAとは日本医師会が開発・公開している日医標準レセプトソフトで、無償提供されています。ORCA以外にも数十社のメーカー製レセコンがあり、各社ごとに機能やサポート内容が異なります。ORCAはソフト自体は無料ですが、導入支援や保守は認定事業所の有償サポートが必要になる場合があります。一方、メーカー製は独自機能や手厚いサポートを備える反面、ライセンス費用や月額料金が発生します。
提供形態(システム形態)
オンプレミス型(院内サーバー設置型)とクラウド型に分かれます。オンプレミス型はクリニック内にサーバーやネットワークを構築して運用する方式で、ネット不通でも院内で完結する安心感があり、安定性やカスタマイズ性が高い反面、初期導入費用や保守コストが大きくなりがちです。
クラウド型はインターネット経由でサービスを利用する方式で、サーバーを院内に置かないため初期コストを抑えやすく、常に新しいバージョンを利用できるメリットがあります。ただし、クラウド型はネット接続が不可欠であり、通信障害時には使えないリスクも考慮が必要です。
レセコンを導入するメリットと注意点
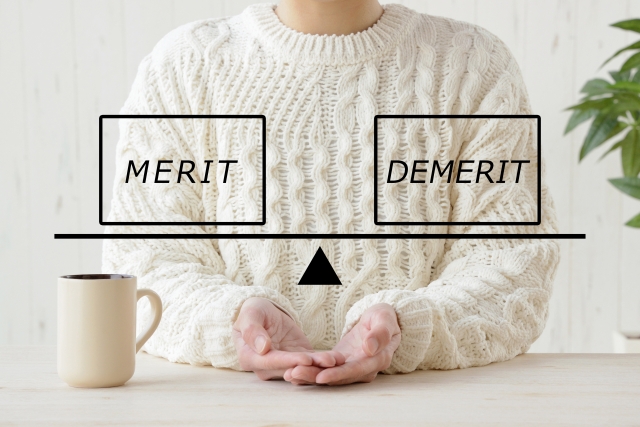
レセコン導入により、クリニックの事務・経営面で多くのメリットが得られます。主なメリットをまとめると以下のとおりです。
- 保険請求業務の効率化
- 入力ミス・漏れの防止
- 人件費・コスト削減効果
- スタッフ・医師の負担軽減
費用対効果の観点では、レセコンに投資することで削減できる人件費やミスによる損失を考慮すると、そのメリットは大きいといえます。仮にレセコン未導入であれば、レセプト作成のために経験豊富な事務スタッフを増員したり、手計算ミスで返戻された請求の再処理に時間を取られたりするリスクがあります。
レセコン導入により事務作業時間が大幅短縮され残業代が減少し、請求漏れの防止で収入機会を逃さない効果が期待できます。特に診療報酬は2年ごとに改定がありルールが複雑化しますが、レセコンはアップデートにより新ルールに対応してくれるため、安定した請求業務が可能になります。
以上を踏まえると、製品ごとの価格差はありますが導入コストは早ければ数年で回収できる投資と考えてよいでしょう。
はい、患者さんにとってもメリットがあります。
まず、レセコン導入により受付から診療、会計までの流れをシステムで一元管理できれば会計処理のスピードが上がり、会計窓口での待ち時間短縮につながります。
次に、請求ミスの防止によって患者さんへの過誤請求や後日の返金対応といったトラブルが起きにくくなります。レセコン導入による業務効率化はスタッフの余裕にもつながり、結果的に患者さんへの接遇やケアの質向上にも寄与するでしょう。
レセコン導入にあたっては、事前にいくつか注意すべきポイントを確認しておきましょう。
- 既存システムとの互換性があるか
- クラウド型、オンプレ型かといった提供形態をどうするか
- 直感的で使いやすいか
- 点数改定や制度変更に迅速に対応してくれるか不具合やトラブルの際、素早く対処してもらえるサポート体制があるか
自院の規模や運用フローに合った製品を選ぶことで、導入後のトラブルや追加の出費を防ぐことができます。
レセコンの選び方と導入の流れ

多くのレセコン製品は電子カルテとデータ連携できるよう作られており、受付情報や診療記録をレセコンに自動転送して会計処理に活かすことができます。
既存の電子カルテがある場合は、そのカルテとデータ連携できるレセコンを選定することが大切です。メーカーごとの相性もあるので、導入前にベンダーへ確認しましょう。
レセコンを選ぶ際には、次のようなポイントを比較しましょう。
- 必要な機能:基本機能(受付・会計・レセプト作成)や返戻防止のチェック機能など付加機能
- 電子カルテなどとの連携:使用中または導入予定の電子カルテと連携可能か
- 操作性(UI/UX):画面の見やすさや操作のしやすさ
- 導入コスト:初期費用とランニングコスト(月額料)
- サポート体制:トラブル時のサポート
- セキュリティ
- 法改正への対応力
各社のカタログやホームページだけではわかりにくいこともあるので、実際にデモ体験をしてみるのもおすすめです。価格やスペックだけでなく、長期的な運用のしやすさやサポート品質にも注目することが大切なポイントです。
レセコン選びに悩んだら、以下のような専門家や経験者に相談するとよいでしょう。
- クリニック開業コンサルタント
- レセコンメーカーや販売代理店
- 開業済みの先輩医師
- 信頼できるITに詳しいスタッフ
このように、専門家や先達の力を借りて情報収集することが大切です。複数のベンダーの製品を比較できる展示会やセミナーに参加することで、実際の操作感を体験することもできます。
レセコン導入までの一般的な流れは下記のとおりです。開業スケジュールに合わせ、計画的に進めましょう。
- 製品リサーチとベンダーの選定
- 契約と導入計画の策定
- 機器設置・設定と研修
- 試験運用と本稼働開始
- アフターフォロー
特にスタッフ研修と慣熟期間の確保が重要で、余裕をもった導入準備と初期の丁寧なトレーニングが、レセコン活用成功のポイントといえます。
編集部まとめ
レセコンは、診療報酬の請求業務を効率化し、クリニック全体の運営を支える重要な基幹システムです。正確かつスムーズな請求処理を実現するためにも、新規開業時から導入を検討することが望ましいでしょう。
電子カルテとの違いを理解し、連携や使い分けを工夫することで診療と経理の両面における業務効率化やサービス品質向上が期待できます。
結果として、患者さんの満足度やクリニックの経営安定にもつながるので、各製品の機能やサポート体制をしっかり比較し、自院に適したシステムを選びましょう。











